結論:睡眠が大切
この記事は5冊の本を読んだ結果、この考えに至りました。
子育て中の同志たちの参考になれば、嬉しいいです。(2025.4.15)
0〜5歳 賢い脳のつくりかた
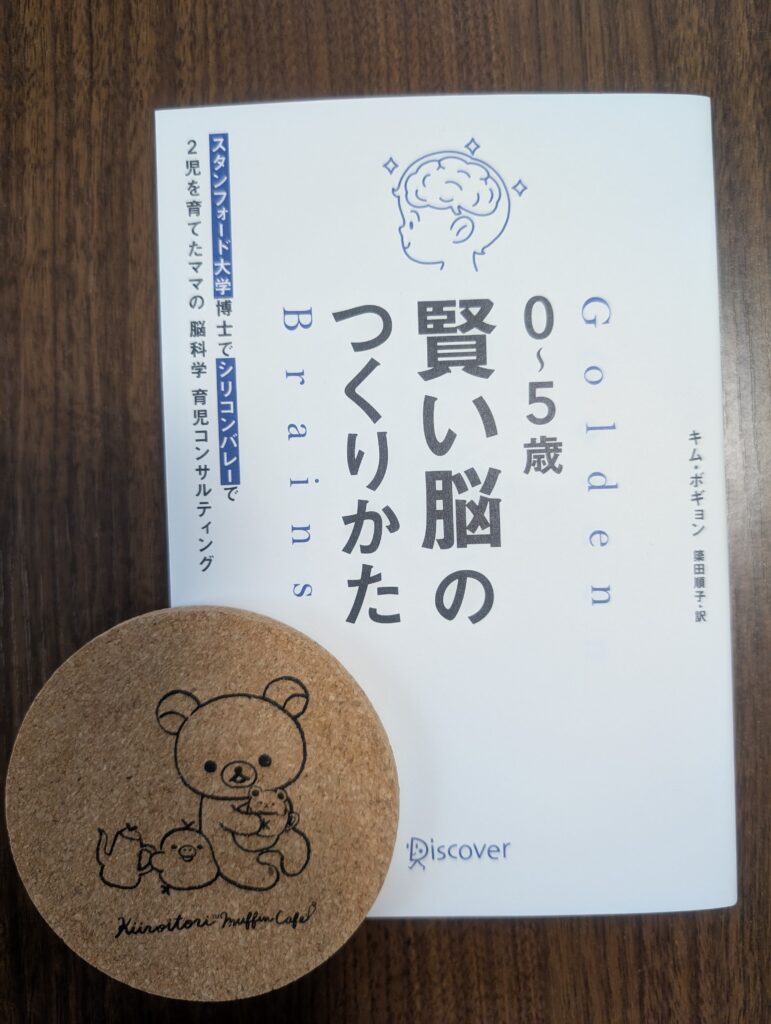
どんな本
0〜5歳の子どもを育てる親に、脳の発達について書いた本。

2部構成です。
1部は脳の基礎について、2部は才能について基礎されてるよ。
伝えたいことが明確で、分かりやすくて読みやい本でした。
ぺいぺーが学んだこと
脳の基礎を作るために、睡眠、食事、運動 が大切。
才能を育てるために、遊び、読書、デジタルメディアが大切。

太文字について詳しく記載します。
睡眠について
家庭環境や親の行動習慣が、子どもの睡眠不足の原因になっている
睡眠は脳のメンテナンス時間で、睡眠不足は肥満リスクや死亡リスクに影響する。
睡眠不足の改善はADHDの症状を緩和する。
睡眠の推奨時間は、アメリカ国立睡眠財団を参考にされることが多い。(下記の表を参照。)
睡眠での親の役割は寝かしつけることではなく、よく眠れる環境を作ること。
健康な睡眠パターンをつくる7つのテクニックがある。
睡眠時間の目安(アメリカ睡眠財団)
0〜3ヶ月 14〜17時間
4〜11ヶ月 12〜15時間
1〜2歳 11〜14時間
3〜5歳 10〜13時間
6〜13歳 9〜11時間
14〜17歳 8〜10時間
「睡眠が大切」と書いてある本は多いね。

多いね。
この本に書いてある、睡眠のオススメのテクニックを次項に記載するね。
睡眠7つのテクニック
①朝、余裕を持っておきる。(30分ずつ早めなが徐々に子どもを慣らす。)
②午前中に日差しを浴びる。(日光がメラトニンの分泌を改善する。)
③お昼寝や、休息時間をとる。(夜間睡眠の補助として個別の調節が必要。)
④夕方、眠くなる環境をつくる。(食事量やタイミング、照明、電子機器の使用等に注意する。)
⑤夜、1人になれる時間をつくる。(子どもが1人で寝ることができるように、徐々に教えていく。)
⑥規則的なリズムをできるだけ守る。(週末も平日と同じ生活リズムになるように心掛ける。)
⑦自分自身の睡眠リズムを見直す。(親自信の睡眠習慣も改善する。)

親の睡眠習慣の改善が必要だって!

スイマセン。
寝る前に隠れてスマホのゲームをしてます、、、
食事について
健康で正しい食生活は、一生健康を守ってくれる。
健康は食べ物で決まり、食べ物はその人の未来をつくる。
バランスよく食べることが大切で、「◯◯健康法」の様な情報におどらされない。
ネガティブな感情を解消するための食事(感情的摂取)に注意。
感情的に食べさせる親が、感情的に食べさせる子どもをつくる。
健康を守る食習慣には4つのテクニックがある

子どもに限らず、食事は大切だね。

「医食同源」て知ってる?

イショク ドウゲン。
何かカッコイイひびきだね!
健康を守る食習慣には4つのテクニック
①食事の時間帯を決める。(食事のリズムが安定すると食事量なども安定する)
②健康的なメニューを提供する。(多様な食材を多様な方法で根気よく経験させるとを心掛ける)
③マナーを守って楽しく食事をする。(子どもは親の行動を真似しながら覚える)
④栄養素と食べ物について一緒に学ぶ。(子どもは経験しながら学ぶ)

食事は毎日するよね。
子どもが興味や感心を持ってくれれば良い教材になるかもね。

うちの子ども達は、まだ小さいから、今後の成長に期待しよう。
運動について
子どもは動きながら学んでいる。
運動習慣は、認知機能や記憶機能を活性化する。
運動は一番簡単で、一番大きな効果を見せる未来への対策。
外遊びは集中力を回復させる。

上の子、お散歩大好きだよね。
どんどん、連れ出してあげようと思ったよ。

お散歩行く〜!
遊びについて
子どもにとって、楽しさをくれる身体活動はすべて遊び。
子どもは、遊びを通して生きる術を学ぶ
パパとの運動遊びは、感情調節と自己抑制能力が育つ。
パパと運動遊びをする時間が長いこどもは、多動や癇癪の様な行動が少くなる傾向がある。
遊びには、親が押さえておくべき4つのテクニックがある。

わが家の上の子、童謡を歌い始めてから、急にお話が上手になったね。

童謡を通して、言語能力の成長が促されたのかもね。

アイアイ、おサルさんだよ〜♪
遊びの4つのテクニック
①遊びの時間は奪わない。(学習や習い事などを詰め込みすぎない)
②子どもに決めさせて、行動させる。(自分で選択する行動が、自分自身を理解する事につながる。)
③おもちゃでは学べないことがある。(子どもは、環境に合わせて、遊び道具や遊び方をつくっていく)
④ストレスに耐える力を育てる。(遊びは子どもの心を守ってくれる。遊びはポジティブな気分を高める、不安定やストレスを克服してくれる。)

わが家の上の子、時々おもちゃ よりも、おもちゃ の箱で遊んでるよね。

環境にあわせた遊び方を開発してるね。
読書について
読書は未来へのプレゼント。
読書(一部、読み聞かせを含む)は、言語能力、表現力、共同注意力、認知的共感能力、情動的共感能力が発達する。
アメリカ小児科学会では、0歳から読み聞かせを推奨している。
子ども読書好きにするコツは5つある

わが家の上の子は、すでに本好きだね。

好きなのは、絵本を読んでもらうこと。
そのうち自分でも読めるようになると、嬉しいな。
子どもを読書好きにする5つのコツ
①0歳から読書をはじめる。(赤ちゃんと一緒に過ごす時に、話しかける内容がなければ、代わりに読み聞かせをする。)
②本と特別な関係を結ぶ。(子どもの読書力は、魂を奪われる様なお気に入りの本が見つかると、自然と上昇する。)
③本と人生をつなげる。(子どもが興味を持ってくれる本を選ぶ。)
④子どものスピードに合わせる。(選んだ本に子どもが興味を持つまで待つ。気にいらない場合もその子の個性なので問題ない。)
⑤思い切って失敗してOK(脳の発達に効率を求めても、思い通りは難しい。)

子どもは文字が読めなくても、本をめくる事、挿絵を眺めること、で十分楽しんでいるんだって。

上の子は絵本の扱いが、雑になりがち。
おもちゃの延長になっているのかな?
大切に扱ってほしい。

激しく同意!
以前、読んだ「0〜5歳児のよくわかる絵本読み聞かせ」って言う本に、絵本の取り扱いについて、参考になる記載があったよ。
残念ながらこのブログでは、詳しくは書いてません。
デジタルメディアについて
デジタルメディアに触れる時間が増えるほど、子どもの言語の発達が遅延する。
子どもと直接会話しない言語刺激は、言語の発達には役に立たない(親が誰かと電話している声、テレビの声etc)
乳幼児のためのデジタルメディア利用ガイドラインがある(アメリカ小児科学会発表)

ガイドラインの内容を記載します。
乳幼児のためのデジタルメディア利用ガイドライン(アメリカ小児科学会発表)
①18ヶ月未満の子どもはテレビ電話以外のデジタルメディアへの接触は制限する。
②18ヶ月から24ヶ月の子どもにデジタルメディアを見せたい場合には、良質なコンテンツを選別し、子どもと一緒に見ながら、理解できるように助ける。
③2歳から5歳の子どもには1日1時間未満、良質なコンテンツを見せる。子どもと一緒に見ながら内容を理解し、実際の生活につなげて考えられるように助ける。
④6歳以上の子どもは利用時間と、デジタルメディアの種類など、一貫した利用の規則を決める。

スマホを子どもに預けると、しばらく遊んでくれるから楽だけど、やっぱり良くないんだね。

ジョブズは子どもにiPhoneを持たせなかったのは有名な話だよね。
子育てを変えれば脳が変わる
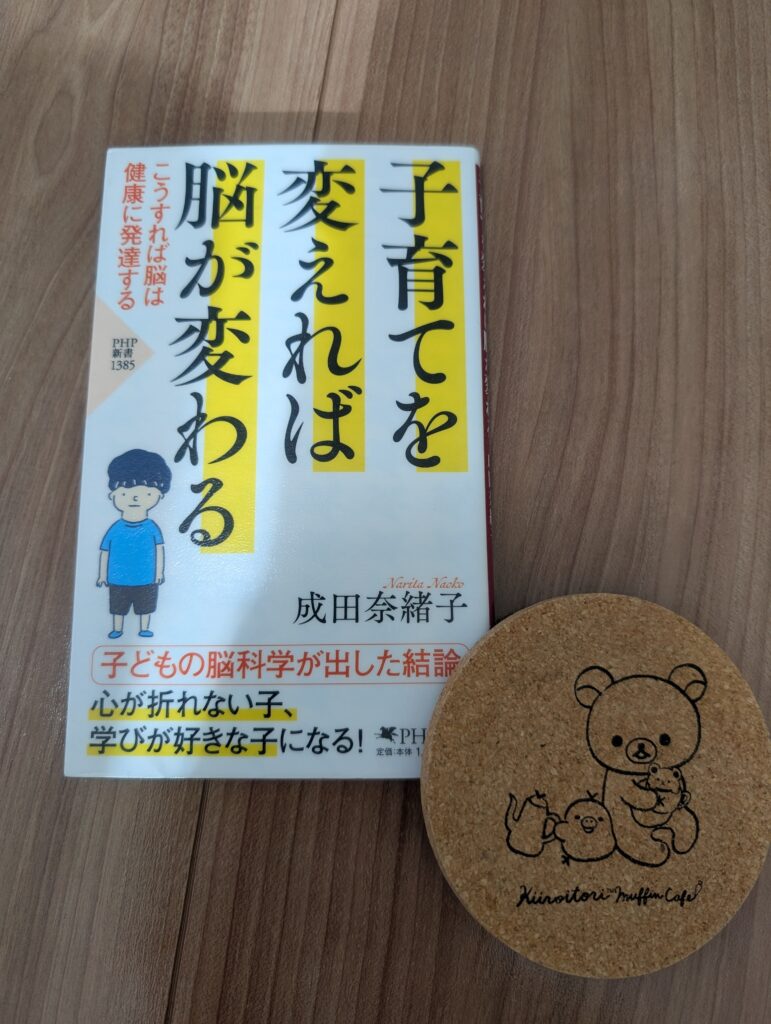
どんな本?
脳が育つ順番に合わせた、子育てを紹介した本
著者は脳科学等が専門の小児科医
ぺいぺーが学んだこと
最初の5年で『早寝早起き』習慣をつけることさえ頑張れは、あとは楽。
子育てに伴う無数の「◯◯しなくては」が思い込みだとわかる。
脳が育つ順番と 年齢の目安
間脳脳幹などを育てるコツ(全ての基本)
大脳新皮質などを育てるコツ
前頭葉などを育てるコツ
オススメしないこと

著者曰く「愛情を注ごう! たくさん褒めよう! と書いてある育児本は多いけど、
情動的な事ばかりで、具体論が見えない本が多い」だって。
精神論に対して、手厳しい💧

実際そうだよ。
精神論じゃなく、具体的な手法が欲しい。
脳が育つ順番と 年齢の目安
- 間脳脳幹など(0〜1.5歳)
- 大脳新皮質など(1歳〜18歳)
- 前頭葉など(10〜14歳)
間脳 脳幹などを育てるコツ(全ての基本)
脳は死ぬまで成長する臓器たが、0〜5歳が一番の「力の入れどき」
「力の入れどき」に、規則正しい生活リズムをつくる事が大切。
規則正しいリズム、具体的には6時に起こして8時に寝かす。
睡眠が摂れれば、食事も摂れる。

8時に寝かしつけるの、無理でしょ?

目標8時。
そもそも、日本人全体が睡眠が足りないって書いてあるよ。
数字にとらわれずに、可能な限り早く寝かそう。
大脳新皮質などを育てるコツ
自発的に思考や探究を深める。
家庭での役割を持たせるため、お手伝いをしてもらう。結果として、自己肯定感も高まる。
色々な体験をさせる。
コツは親が一緒に楽しめる事をする。

親の趣味に付き合わせるって事か?

変なのは、やめてね。
すでに、あなたで困ってるから。

・・・・・・・・・・・・・はい。
前頭葉などを育てるコツ
子供が安心感を持てるような声かけをする。
物事を言語で表現する機会や、それをしやすい環境をつくる。

頑張る!
オススメしないこと
父親との触れ合いのため、夜まで起こしておくという事例
→起立性調節障害のリスクが高まる
過度な習い事のハシゴ、過度な早期教育の事例
→学童まではうまくいくが、思春期頃にトラブルリスクが高まる
などなど

各家庭には事情があるからなあ、、、
何とも言えないな〜

記載の事例が、絶対にそうなると書いてあるわけでは無いので、勘違いしないで。
この本は、著者の臨床での経験も含めて、記載した内容だよ。
著者からの提案の1つとして、受け取るべきで、
該当事例の方が否定されているわけでは無いよ。

カミさん、大人だな❤

デカいキリンを世話して、大人になりました。

・・・・・・・・・・・・・・お世話になります。
著者の別の書籍
『対応力について、子どものために大人から変わる
子どもの脳を発達させるペアレンティングトレーニング』
も気になるから、後で読んでみるよ。
次の本は、、、
子どもたちに 大切なことを 脳科学が 明かしました
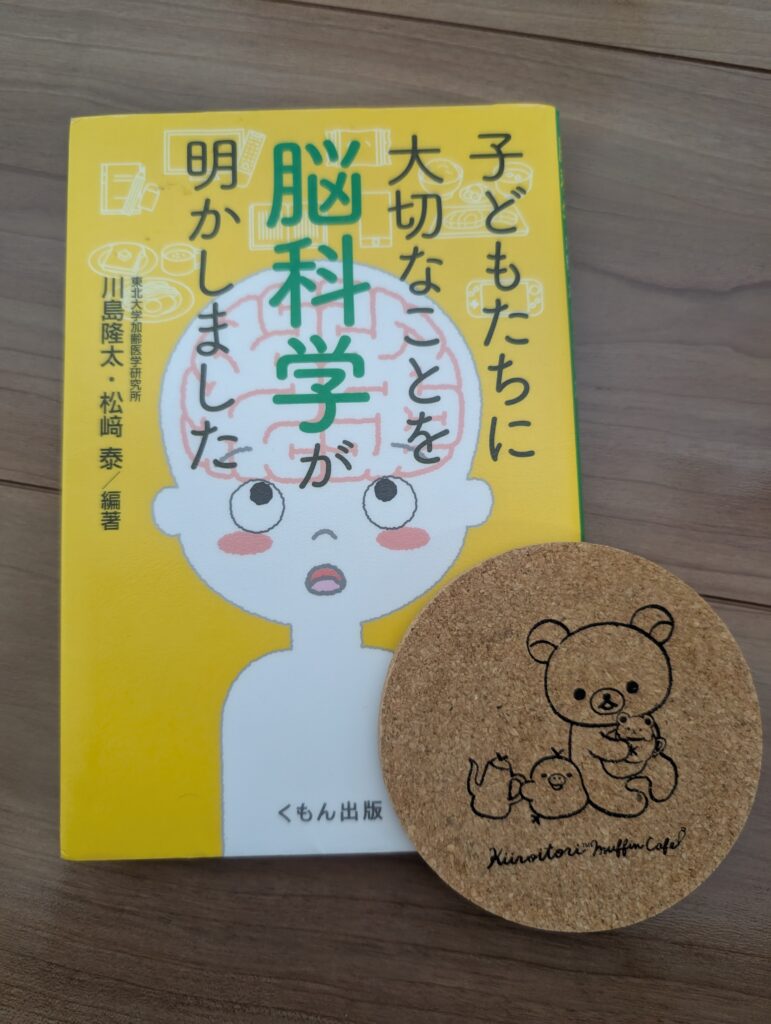
どんな本?
子供の脳発達についての研究結果と、コラムで構成された本

あとがきに「早寝早起き朝ごはん」「家族全員で本を読もう」と著者からのメッセージが記載されていて、印象に残りました。
ぺいぺーが学んだこと
育児で オススメすることに、睡眠の管理と読み聞かせがある。
育児で オススメしないことに、TVの見すぎ、YouTubeの見すぎなどがある。
育児で オススメすること
寝る子は育つは本当(不眠は海馬発達の妨げ)
読み聞かせは、言語以外にも、記憶、感情の発達に有効である。
読み聞かせは、親にとってもプラスに働く(育児ストレス減少効果)。
たたし、読書し過ぎて睡眠不足だと、成績が落ちる。
(中学生を対象にした研究結果にて)

睡眠の管理は、色々な本に書いてあるよ。
この本の著者は、読み聞かせもオススメしてるよ。
オススメしないこと
テレビを3時間以上のみる子供は、そうでない子に比べて、言語能力が低くなる。
理由は脳への刺激になる、勉強、運動、游び、をする時間が減るため。
マルチタスクをする人ほど集中力が低い傾向になる。
テレビを観ながらの「ながら作業」もマルチタスクに当てはめる。

上記の記載、、、
普通の生活でよくある状況なんだけど、、、

日常生活で見られる状況を
研究対象として調べて、
実際に成果をまとめて、
出版した事に、意義があるんだよ。

さすが!理系!
YouTubeも見過ぎに注意。
ゲームもやり過ぎに注意。
ゲームに関しては、依存のリスクがあるので注意。
スマートホン利用も、やり過ぎ注意。
スマホに関しては、睡眠時間が同じ位の子供で比べても悪影響がでていた。
(スマホでYouTube見てた場合の…記載なし)

何か言うことある?

ゲームやり過ぎで、スイマセン。
YouTube見過ぎで、スイマセン。
勉強は脳の発達によい影響を与えるが、効果は科目によって異なる。
(いろいろな科目に取り組む方がよい)
親子の触れ合い、会話は、脳の発達に影響する。
ほめる等のポジティブな子育ては、記憶や感情の発達により良く影響する。

出来そうなとこから、子育てに取り入れる!
脳と子どもの専門化が知っている 子どもの脳がみるみる育つ新習慣
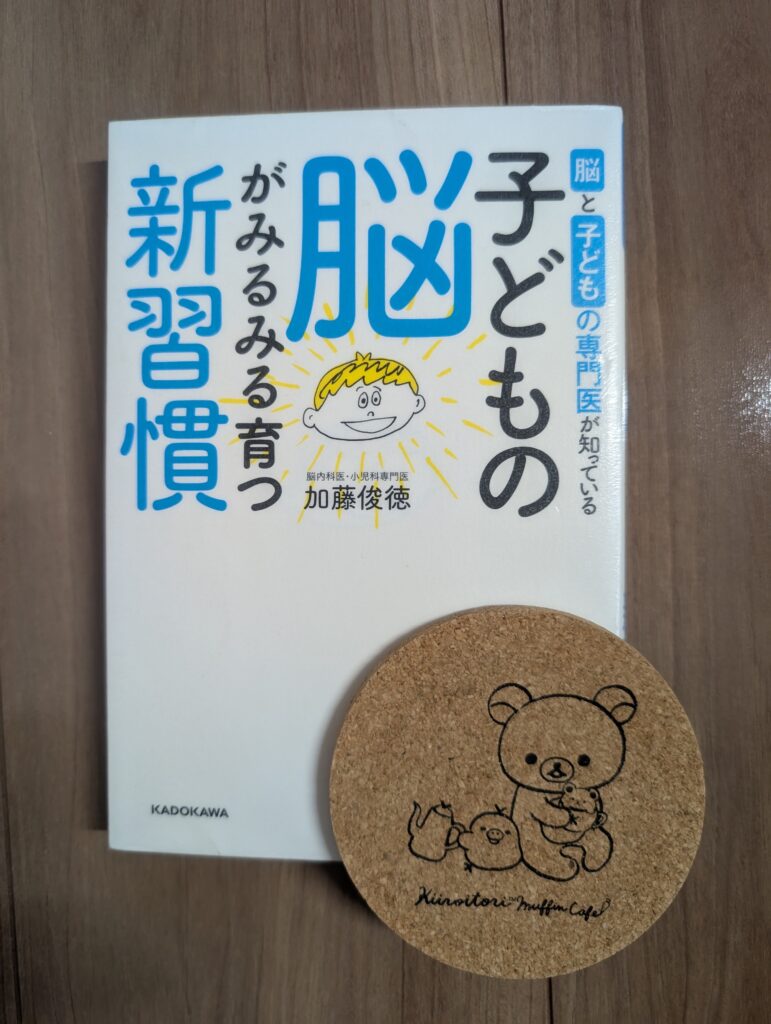
どんな本
脳内科医で小児科専門医が書いた、すぐできる脳を育てるちょっとした習慣を書いた本

具体的な悩みについて、簡潔に解説していて、とても読みやすい本でした。
「発達障害かも」という親の不安を解決してくれる内容もありました。
ぺいぺーが学んだこと
声かけについて。
睡眠が大切。
おふざけについて。
忘れ物について。
習い事について。
声かけについて
怒っている子どもに対して有効なのは静かで落ち着いた声かけ。
子どもは「聞く」ことが苦手で、状況をうまく理解できない事が、かんしゃくの原因になるケースがある。
睡眠が大切
親自身が、決まった時間に寝る習慣を心がける。
睡眠リズムが整えば、1日のリズムが自然に整う。
10歳以下の子どもの場合、睡眠時の呼吸に影響する病気に注意する。(扁桃腺肥大症 アデノイド増殖症)
睡眠時間の目安は(アメリカ睡眠財団)
0〜3ヶ月14〜17時間 4〜11ヶ月12〜15時間
1〜2歳11〜14時間 3〜5歳10〜13時間
6〜13歳9〜11時間 14〜17歳8〜10時間

睡眠が大切は色々な本が書いてるね。
アメリカ睡眠財団、また出てきた。

確かに。
睡眠が大切、何度も重複して出てくる。
「おふざけ」について
「おふざけ」は親の気を引きたいから。
「落ち着きなさい」には意味がない。
「おふざけ」に同調して、一緒楽しく遊ぶことも、選択肢の一つ。

上の子は、下の子が生まれてから、「おふざけ」が酷くなった気がする!

ぺいぺーも、「おふざけ」が酷い時があるよ。
気をつけてね♪

お、おう。
忘れ物について
叱っただけで苦手は克服できない。
こまやかなサポートで、日々の習慣として繰り返すことで、自立できる。

理由は忘れたけど、小学4年生の時に何故か忘れ物が多かった。
気づいたら直ってた。

いつも、しっかりしてるから意外!
習い事について
体を動かすほど、子どもの脳は成長する。
脳は、楽しい時や心地いい時に成長する。
芸術、音楽、運動など、子どもの興味に合わせて選ぶ必要がある。
習い事は能力の習得でなく「脳への刺激」に意味がある。
習い事は続かない方が当たり前なので、辞めたことを責める必要はない。

わが家では、子どもが興味を持ちそうな習い事を探してみます。
パパは脳研究者
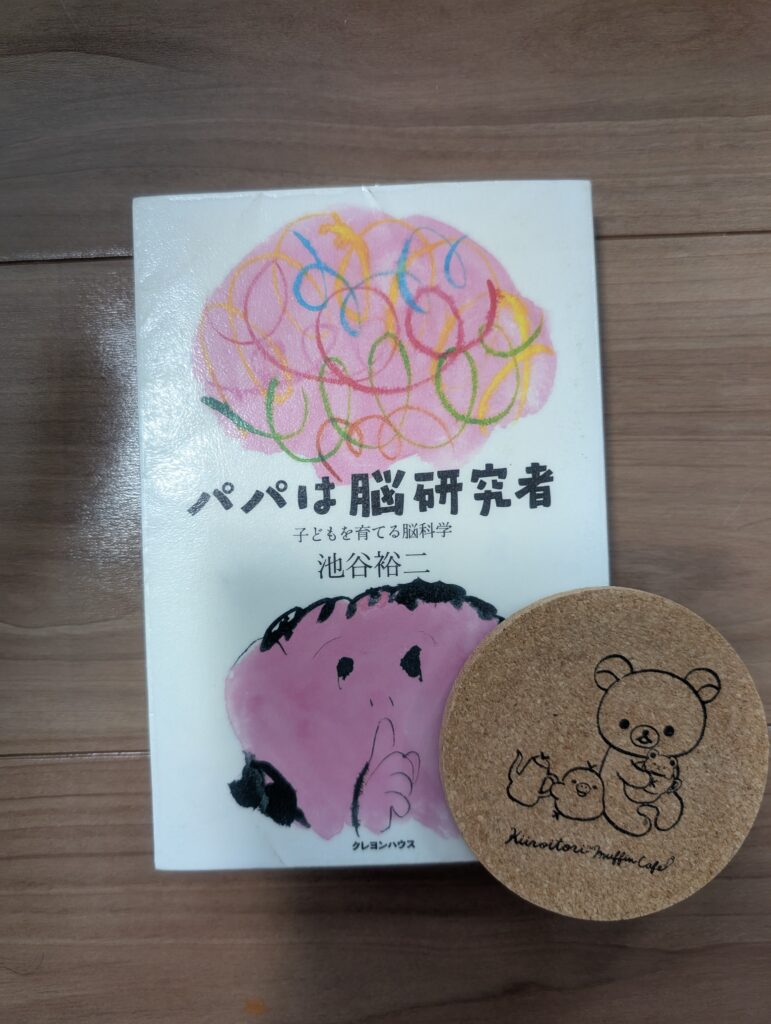
どんな本
脳研究者の個人的な育児記録であると同時に、脳の発達を通じて脳の働きについて考えるための解説書。
ぺいぺーが学んだこと
育児の本質は「親なんていなくても立派にやっていける子になる」ように導くこと。
親がしっかりと話しかける限り、言葉の成長にほぼ男女差はない。
オキシトシンには意外な効果があり、仲の良い人には強い信頼関係を結ぶようになるが、そうでない人に対しては疎遠になり、しばしば攻撃的になる。

パパに対してはイライラするのは、オキシトシンが原因かも?

著者によると、子供が生まれる前に母親がオキシトシンが作る「仲間の輪」に入らないと、育児の難易度が上がるんだって。
実体験として同感💦

この本の記載はこれだけ?

脳科学者の父親の視点から子どもの成長を記載した良書です。
ただしhow to本ではないから、僕のブログでは少なめ記載になりました💦
まとめ
子育てと脳の関係について本を5冊読んだ結果、多くの本で睡眠について記載があった。
ぺいぺーは、睡眠リズムと睡眠時間の確保が、子育てにはとても重要と結論づけました。

子育て中の仲間たちに、
役に立てば嬉しいです!



コメント